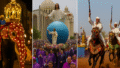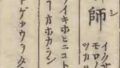夏本番を迎える8月上旬、日本各地の神社では伝統ある祭典が盛大に執り行われます。この期間(2025年8月4日~10日)の中から、東日本・中部・西日本それぞれの地域を代表する3つの祭典をご紹介します。古くから地域に根差した夏祭りは、神への感謝や季節の節目を祝う行事として受け継がれてきました。歴史と文化が息づく祭典の魅力を、東西の地域バランスに配慮しながらたっぷりお伝えします。
① 鶴岡八幡宮(神奈川県鎌倉市)
ぼんぼり祭
開催日: 2025年8月6日(水)~9日(土)
場所: 鶴岡八幡宮(神奈川県鎌倉市)
夕闇とともに灯された鶴岡八幡宮の「ぼんぼり」。境内には約400基もの絵笠提灯が並び、幻想的な夏の風物詩となる。巫女たちが奉納された灯りを丁寧に点し、参拝客は静かな祈りと芸術の調和を堪能します。
鎌倉の夏の風物詩「ぼんぼり祭」は、昭和12年(1937年)から続く鶴岡八幡宮の伝統行事です 。期間中、境内や参道には鎌倉ゆかりの文化人や各界著名人が揮毫した書画を掲げた約400基のぼんぼり(絵灯籠)が立ち並び、夕暮れとともに一斉に柔らかな灯がともされます 。昼間は歴史ある社(やしろ)の風情を感じながら、夜には一転して優美で幻想的な光景が広がり、訪れる人々の目を楽しませてくれます。
祭典期間中には神社にて3つの神事が執り行われるのも見どころです。8月6日の夏越祭(なごしさい)、8月7日の立秋祭(りっしゅうさい)、そして8月9日の実朝祭(さねともさい)と、日替わりで厳かな祭典が続きます 。いずれも鶴岡八幡宮の由緒に深く関わる神事で、静寂の中にも凛とした空気が流れ、鎌倉らしい歴史と祈りの時間を感じることができます。期間中は参道周辺に屋台も並び、提灯の灯りを眺めながら夏祭り気分で散策できるのも魅力です 。
ぼんぼり祭は、鎌倉市民にとって夏の到来を告げる大切な行事であり、地域の文化芸術とも結びついた特色あるお祭りです。「静かな夏の祈りと芸術の祭典」として広く知られ、観光客にも人気が高まっています。鶴岡八幡宮という歴史的な神社の境内に揺れるやさしい灯りは、忙しい日常を忘れさせてくれるような心洗われるひとときを与えてくれるでしょう。
② 新潟祭り(新潟県新潟市) -
住吉祭
の伝統を受け継ぐ港町の夏祭り
開催日: 2025年8月8日(金)~10日(日)
場所: 新潟市中央区古町通・萬代橋周辺(新潟県新潟市) ※主催: 新潟市・新潟まつり実行委員会
日本最大級の民謡流しである新潟祭り「大民謡流し」の様子。夜の萬代橋上を埋め尽くす約1万5千人の踊り手たちが揃いの浴衣で新潟甚句や佐渡おけさを踊り、市民総出で夏祭りを盛り上げます 。
毎年8月上旬に開催される新潟祭りは、新潟市を代表する大規模な夏祭りです。昭和30年(1955年)に住吉祭・商工祭・川開き・開港記念祭という歴史ある4つの祭りを統合して第1回が行われた経緯があり、港町・新潟ならではのスケールの大きなイベントとして定着しています 。起源の一つである住吉祭は江戸中期の享保11年(1726年)、北前船交易で繁栄した廻船問屋が航海安全を祈願して始めた祭礼と伝えられ、古式ゆかしい行列や水上神輿渡御の伝統が今も受け継がれています 。江戸時代には湊祭とも呼ばれ、七夕の頃に行われたため「七夕まつり」とも言われたそうです。当時は神輿を車輪付きの御座船に乗せて町内を巡行し、夜には無数の灯籠や提灯が灯され、その火影は対岸の佐渡島からも見えたと伝えられます 。こうした歴史とともに、新潟祭りは時代に合わせて形を変えながらも地域の誇りとして受け継がれてきました。
現在の新潟祭りは3日間にわたり多彩な催しが繰り広げられます。初日金曜夜には、新潟甚句や佐渡おけさにあわせて市中心部を舞台に1万5千人規模で踊り歩く**「大民謡流し」**が行われ、萬代橋や繁華街のあちこちで踊りの輪ができあがります 。浴衣姿の踊り手たちによる日本最大級の民謡流しは壮観で、観衆も飛び入り参加できる開放的な雰囲気が魅力です。
2日目・3日目には、この祭りのハイライトである**「住吉行列」が登場します。鎧兜に身を包んだ武者や神職、稚児などが古式ゆかしい装束で練り歩く行列は全長1kmにも及び、市内をゆったりと巡行します 。特に先頭を進む騎馬武者や神輿を護る一団の姿は迫力があり、江戸絵巻を彷彿とさせます。また、2日目(土曜)の正午過ぎには信濃川の川面を渡る「水上みこし渡御」も必見です 。神輿が御座船に乗せられて川を横断する様子は、港町・新潟ならではの伝統行事で、川岸にはそれを一目見ようと多くの見物客が集まります。祭りのフィナーレとなる3日目夜には、信濃川河畔で約1時間にわたる大花火大会**が開催され、ナイアガラの仕掛け花火や音楽とシンクロしたスターマインが夜空と川面を華麗に彩ります 。
新潟祭りは、古き良き伝統と現代の市民参加型イベントが融合した祭典として、地元では「みなと町新潟の夏を象徴する祭り」として親しまれています。北前船で栄えた往時の繁栄を今に伝える行事の数々は、新潟の歴史と誇りを再認識させるものです 。地域の人々にとっては一年の中でも特別な期間であり、総踊りや神輿を通じて世代を超えた絆を深める場ともなっています。訪れる観光客にとっても、日本海側最大の港町ならではの活気と伝統を一度に味わえる絶好の機会でしょう。
③ 多賀大社(滋賀県多賀町)
万灯祭(まんとうさい)
開催日: 毎年8月3日~5日(2025年は8月3日(日)宵宮~5日(火))
場所: 多賀大社(滋賀県犬上郡多賀町)
多賀大社の万灯祭では、夜の境内に1万を超える提灯が灯り幽玄な光景が広がります 。神社の神門へと続く参道両脇にずらりと吊るされた提灯の列は圧巻で、多くの参拝者がその幻想的な雰囲気を楽しみに訪れます。
滋賀県湖東地域に鎮座する多賀大社は、伊邪那岐命・伊邪那美命の夫婦神を祀る日本有数の古社です 。古くから「お多賀さん」の名で親しまれ、延命長寿や縁結びの御利益で知られる由緒正しい神社ですが、その夏の例祭こそが万灯祭です。毎年8月3日から5日にかけて行われる万灯祭は、平安時代の御霊会に由来するともいわれ、祖先の霊を慰め五穀豊穣を祈る意味合いも持つ伝統行事です。
万灯祭最大の特徴は、一万余りの提灯に火が灯される幽玄な夜の光景にあります 。祭の初日には、祭神が降臨した地と伝わる杉坂山で御神火祭が斎行されます。古式に則り燧石を切って浄火をおこし、その火を里宮である調宮神社(ととのみやじんじゃ)を経て多賀大社の本社へと運び入れると、宵闇の19時、一斉に境内の提灯に明かりが灯されます 。境内入口の太鼓橋(普段は通行禁止の反橋)もこの期間だけ特別に開放され、参拝者は揺れる提灯の下を渡って本殿に向かいます 。提灯の優しい灯りに照らし出された社殿や石畳はなんとも幻想的で、その様子をひと目見ようと毎年多くの人々が全国から訪れます。
祭期間中、点灯された提灯の明かりに包まれた境内では、本殿祭が厳かに営まれるほか、雅楽や巫女神楽などの奉納行事も行われます 。参道には夜店が立ち並び、万灯市と呼ばれる市も開かれて賑わいを見せます 。家族連れや地元の氏子たちがゆったりと提灯を眺めながら歩く姿は、どこか懐かしく温かな夏の夜の情景そのものです。
この万灯祭は、多賀大社に祀られる伊邪那美命が黄泉の国の大神・**「黄泉津大神(よもつおおかみ)」として祖先の霊を守護するとされることにちなみ、祖霊への感謝を捧げるお祭りでもあります 。灯明のひとつひとつには先祖や故人への想いが込められ、参列者は手を合わせて無病息災や家内安全を祈願します。お盆を前に行われるこの祭礼は、地域の人々にとって「ご先祖さまを慰める大切な行事」**として位置づけられており、滋賀県内でも指折りの夏祭りとして広く知られています。
多賀大社の万灯祭は、その壮麗な灯りの光景から「灯の祭典」とも称されます。昼間の夏空の下に見る多賀大社も趣がありますが、夜の万灯祭でしか味わえない厳かな美しさは格別です。古社ならではの伝統儀式と1万の灯火が織りなす情景は訪れた人の心に深く刻まれるでしょう 。地域住民にとっても誇り高い祭典であり、遠方からの参拝客にも日本の伝統美と信仰心の強さを感じさせてくれるはずです。
以上、東日本(関東)の鶴岡八幡宮ぼんぼり祭、中部(新潟)の新潟祭り、西日本(近江)の多賀大社万灯祭の3つの祭典をご紹介しました。それぞれの祭りは地域の歴史や風土を背景に独自の発展を遂げており、季節と共に受け継がれてきた地域の宝物です。八幡宮の静謐な灯りから、港町の活気あふれる踊り、古社の幽玄な提灯の海まで、夏祭りと一口に言ってもその表情は実にさまざまです。
どの祭典も、地元の人々の厚い信仰と誇りによって長年守られてきました。祭りの太鼓や笛の音、お神輿を担ぐ掛け声、提灯の明かりに照らされた笑顔――それらはきっと見る人の心にも夏の思い出として刻まれるでしょう。暑い夏のひととき、日本の伝統的な神社祭典を巡り歩けば、地域ごとの文化や人々の絆の深さを肌で感じることができます。ぜひ皆さんも機会があれば足を運んでいただき、それぞれの土地ならではの夏祭りの魅力を体感してみてください。きっと忘れられない感動と発見が待っているはずです。地域に根ざした夏の神社祭典が、皆様の旅や暮らしに彩りと活力を与えてくれますように。では、よい夏祭りを!