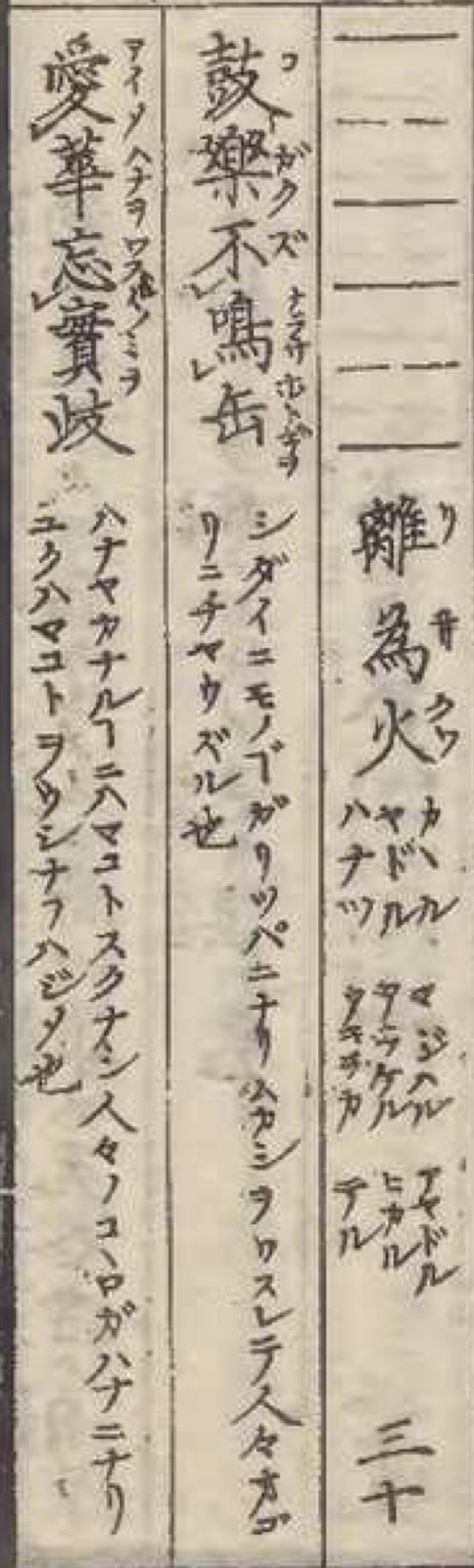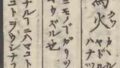周易64卦384爻占断
179、離為火(りいか)5爻
◇ 離とは何か?
離為火(りいか)は「明・文明・付着」を象徴する卦です。
火は自らの力だけで燃え続けることはできず、
必ず何かに宿ってはじめて光となります。
この性質から、離は 明の徳 と同時に
何かに依ってこそ役目を果たす慎み深さ を教えてくれる卦といえます。
火は盛んになれば一気に燃え広がり、
衰えればすぐに力を失う――
その揺れやすさが、離の卦が持つ「明の不安定さ」を象徴しています。
離の教えとは、
明を保ちながら、過剰にも不足にも傾かず、正しい位置で光を放つこと。
そこには節度・謙虚さ・適度のバランスが欠かせません。
⸻
◆ 卦全体が教えてくれること
離の光は明るいものの、その輝きはとても揺らぎやすいものです。
光が揺れれば影も動き、心もまた不安定になります。
ここで説かれる教えは、
「光を扱うには、心の落ち着きこそが必要だ」
という一点です。
明とは単に外を照らすものではなく、
自分の内側――思考・感情・立ち位置――を照らし出す力でもあります。
焦りに駆られたり、気分に任せたりすると、
その光は簡単に曇ります。
冷静さと静かな姿勢が、明を正しい方向へ導くのです。
⸻
◆ 五爻の爻辞と解釈
【爻辞】
「涕(なみだ)を出して沱若(たじゃく)たり。戚(いた)みて嗟若(さじゃく)たり。吉。」
【象伝】
「六五の吉は、王公に離(つ)けばなり。」
■ 解釈
五爻は卦の中心であり、王の位置に相当します。
しかしその本質は 陰柔 で、実力よりも責任が重くのしかかりやすい位置です。
真上から圧迫してくるのではなく、
むしろすぐ下の四爻(=「公」、強く勢いのある存在)から
圧力がかかるため、心が揺れやすくなっています。
そのため爻辞には、
- 涙が溢れるほどの憂え(沱若)
- 心が痛み、思わずため息が漏れるほどの嘆き(嗟若)
が描かれています。
ただし、これは弱さの象徴ではありません。
柔中の徳を保ち、自分の位を慎み深く守ろうとする姿勢 が表れているのです。
四爻は剛健で気性の強い存在ですが、
五爻はあえてこれを押さえ込まず、
適切に「離(つ)いて」協力しながら政を進める 道を選びます。
象伝の「王公に離く」とは、
五爻(王)が四爻(公)の剛を適切に用い、
謙虚さをもって大局を治めるために吉となる、
という意味です。
つまり、
- 王(五爻)は柔で大局をみる
- 公(四爻)は剛で実務を担う
この二つが調和するとき、涙の中から吉が生まれる、というわけです。
⸻
◆ 含まれる教え
- 高位にあっても、強く出る必要はなく、むしろ柔らかい姿勢が吉を呼ぶ
- 謙譲は弱さではなく「明の徳」を守る力
- 苦しさの中でも節度と冷静さを失わないこと
- 周囲の力を適切に借り、独断を避ける
- 悲しみは、次の吉へ向かうための“浄化”として働くことがある
⸻
◆ 仕事
五爻を得たとき、仕事では悩みや負担を感じやすい時期です。
責任ばかりが重く、実力が追いつかないように思える場合もあります。
しかし、その苦しさは
柔の徳を守りながら調整役に回ることで減じていきます。
- 有能な部下や後輩をうまく活かす
- 自分が前面に出すぎない
- 年上・経験者の助力を仰ぐ
こうした姿勢が運気を開く鍵となります。
新規事業や拡張は向きません。
今あるものを丁寧に維持し、少しずつ整理してゆくほうが賢明です。
⸻
◆ 恋愛・婚姻
恋愛・婚姻では、心が揺れやすく、涙することもある時期です。
思うように進まない、迷いや不安が多い――
そんな状態になりがちです。
しかし五爻は 最終的には吉 に落ち着くという特徴があります。
- 最初は障害があっても、後に安定する
- 条件が揃わずとも、粘り強く続けると道が開ける
- 選り好みを続けるより、等身大の相手を受け入れるほうが吉
「泣き泣き嫁ぐ」という表現の通り、最初は苦労があるかもしれませんが、
結果として悪い縁ではないことが多いのです。
⸻
◆ 離為火(五爻)が教えてくれる生き方
離の五爻は、
弱さに見える涙が、むしろ明を守る力になる
という深い教えを持っています。
責任を背負い、重圧に押され、涙が出るようなときこそ、
人は本当の謙虚さと柔らかさを取り戻すものです。
- 強がらない
- 無理に押し通さない
- 周囲と調和しながら進む
こうした姿勢が、沈みかけた光に再び命を灯すのです。
火は他に付いてこそ燃えるように、
人もまた周囲とうまく結びつくことで明を取り戻します。
悲しみの中でこそ芽生える「柔の力」。
それを大切にして歩むことこそ、
離為火・五爻が示す人生の智慧といえるでしょう